- 未就学児でグレーゾーン
- 将来について少し不安になってきた
- 漠然としすぎていて何を知ればいいのかわからない
息子は現在3歳2ヶ月
3歳児検診にて療育の話が出ました
3歳前後だと療育が必要かどうかはとても微妙らしく、私自身も

- まだ年齢的に発達途中で出来ていないだけでしょー?
- 必要なくない?
- なんか良い話あんま聞かないし…
と思っていました。
元々子どもの発達については
- うちはうち
- なるようなる
- 遅くてもそれも個性
- 病院通ってるし問題ない
というノーテンキ一家でしたが…

⬆︎⬆︎この日を境に

【息子と楽しく過ごしていく為】未就学児でグレーゾーンになる子の特性や、どんな対応をしてあげたらいいのかが知りたい!!
好奇心に火がつき燃え上がりました(今も燃え上がっている最中)
とりあえず本屋!!と、探しに出かけましたが
これが、なっかなか見つからなかった…

1時間以上、極寒の本屋で「そう!こう言う事が知りたかった!!」がまとまっていた本を見つけたので、この記事が私の様に悩んでいる方の購入の参考になればと思います。
知識は武器であり防具だと思います。
医者任せにしないよう、疑問に思ったら質問出来るように。
自分も息子と大きくなっていく為、自分たちの身を守る為に。
「備えておけばいざと言うときにパニック具合を抑えられそう。何もなければそれでヨシ。」そう思い、知ることにしました。
備えておいて損は無いですが、知ることにより不安が増すのも事実です。
実際に私も探してる間/沢山の情報を得ている間は不安で心が沈みました
知ることによって自分を追い詰めすぎてしまう方には向いていないので、ご自分の性格とよく話し合って読んでみてください。
この記事の内容が全てではありません。
私の解釈が違っている場合もありますので、気になる事は調べ直していただけると助かります。
未就学児向け発達支援の本
PriPri特別総集 発達支援 / 世界文化社
保育士さん向けの本ですが、親が見てもとてもわかりやすいです。
発達支援コーナーには小学校以降の子の本が多く、未就学児向けの本はありませんでした(私が行ったそこそこ大きい本屋情報ですが)
保育士資格コーナーにてこの本を発見しました。
- 知識がない人でも一目でわかる
- それぞれれが詳しすぎず、程よい内容で載っている
- 定型発達の子と、困難を抱える子との区別がわかる
- 写真が多く載っているので大変わかりやすい
【知識】読んで知る事が出来た事
発達に障害がある子とは
- 脳の機能に偏りがあることが原因で困難に遭遇する
- 定型発達の子が無意識に取捨選択している事が出来ない

なぜできないのか?疑問でしたが、これを読んで明確になりスッキリしました。
音に困っている子
音の洪水に飲み込まれている
聞こえる全ての音が混ざって聞こえ、指示を聴き取れない。
話を聞いていないと思われやすい

ただ【音が聞こえない】だけだと思っていた…
定型発達の子とそうでない子のそれぞれの【音の聞こえ方音量メーター】が書いてあり、とても想像がつきやすかった。
光や色が苦手な子
情報刺激を過剰に受け取ってしまう
気持ちが落ち着かなくなったり気分が悪くなる
自分が好む視覚刺激だと落ち着くため、くるくるまわったりキラキラした物を好んで眺めたりする子もいる。

ただ眩しい。
慣れれば大丈夫だと思っていた。
定型発達の子とそうでない子の【見え方の違いが写真で比較】されていて、大変わかりやすかった。
落ち着きがない子
待つ事や行動の切り替えが苦手
脳の機能の偏りが原因の為、本人ももどかしさに悩み不安を抱えてる事が多い。
行動を制御できず叱られる事が多く、自尊心が傷つく。

歳を重ね大きくなれば勝手に落ち着く。
しつけで何とかなると思っていた。
落ち着きがない子がどのように意識が逸れて行くのかが【写真とその時のその子の気持ち】が載っていて、わかりやすかった。
ポイント
- その子自身に目を向けて特性を理解
- 現状に合わせた支援を考える事が大切
発達障害の種類と特性
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 学習障害(LD)注意欠陥
- 多動症(ADHD)
- 発達性協調運動症
それぞれの特性が詳しくわかりやすくまとめられている
子どもの困ったことの疑似体験の仕方
- もどかしさプレッシャーにイライラ
- 思うように行かず頭と手が混乱
- 視野の狭さの体験
- 言っている事がわからずモヤモヤ
それぞれの体験の仕方が載っている
簡単な製作物の作り方
- おはな
- さかな
- アイスクリーム
- きのこ
スモールステップで少しずつ達成感を味わう事が大切
それぞれの作り方
制作活動を支援する5つのポイントが載っている
【視覚支援】絵カードの使い方のポイント
目に見えないもの(ここに座って/静かにして/少し待ってなど)を理解する事が苦手な子に有効な支援
【見える化】をして、わかりやすい環境に。
絵カードは子どもにとって楽しいものである事が最も重要
子どもが自然と絵カードにしたしみ、便利さを感じられるように適切な手順で導入する事が大切。
まずは絵カードすき!と思えるようにする
- 初めて使う時は実際の活動をしながら使う
- 使い初めは子どもが好きな絵カード(行動)を中心に楽しく使えるようにする
- 絵カードを使って上手に出来たらたくさん褒める
- 使う→できる→自信が付くの好循環を作る。特性に応じて絵カードをアレンジ
【絵カード】視覚ツールの作り方
- ホワイトボードに貼る
- 一覧式にする
- 卓上式でめくる
- カードをひっくり返すとできたねのイラストになるようにする
- 終了した過程のカードに好きなキャラカードを重ねる
- 手のひらサイズのめくり式
製作物と絵カード(8枚:できたね!/お弁当を机に出すまでの過程/うさぎのイラスト)の例がコピーできるよう、本の最後にコピー用型紙がついている。
混合教育による育ち合いについて
違うことは特別ではない
自然と認め合える関係性を。

落ち着きがないからきっと色々我慢するのは難しいだろうな…という不安はありますが、子ども園に通わせていいのか?という不安は解消されました!!
クラスの雰囲気や会での交流の様子など、写真と共に読み物が載っている。
就学先はどう選ぶか
【4つの選択肢特別支援教育の受け方】
- 通常学級で支援を受けながら学ぶ
- 通常学級で学びつつ通級を利用
- 特別支援学級で学ぶ
- 特別支援学校に通う
困り度によって支援の受け方も様々
相談できるが最終的には保護者の希望が優先される。
就学先が決まるまで、どの時期に何をすればいいのかが載っている。
基本的には一斉授業を前提とした支援
教員が子どもの特性を把握して支援の方法を工夫する
自治体によっては加配の支援員が付く場合もある
週に1〜2度、通常学級から通う。
苦手なことについて丁寧に指導を受ける
自校に通級がない場合、他校まで通うことになる。
グループや個人での支援個別の教育支援計画が立てられる
学習上や生活上の困難を改善するスキルを学ぶ
その子に合わせた細やかなフォロー
1クラスの定員が8人個別/学年別/学習進度別に分かれて授業が進められる
通常学級での交流授業もカリキュラムにある地域によって入りやすさが違う
特別支援学級がない学校もある
そのため学級がある学校まで通うことになったり、希望者が多くて入りにくい市町村は検査結果の数値などで基準を設けているところもある。
障害の過程による就学基準で入学
身辺自立に支援が必要と判断された子が通う
自立に向けての支援に重き個別の教育支援計画を作成卒業後までを見越したきめ細かな支援計画を立てる
高等部に進むと職業訓練も増える
就職につながる作業学習が増え、就労を目指すことに重点を置いた高等特別支援学校もある。
特別支援学級の現場の様子
見学風に特別支援学級の1日の流れが載っている
時間ごとに先生と生徒の様子が細かく限られていてとてもわかりやすい
将来への見通しマップ
〜6歳/〜12歳/〜15歳/〜18歳/18歳〜と、成長するにしたがい将来の選択肢に広がりがある
それぞれの道のりが図によりわかりやすく載っている
受容へ向かう保護者の心境
保護者の声/子どもの発達障害を受容する心理プロセス/需要を支える保育社のサポートが載っている
おわりに
- どんな風に困難なのかを理解出来た事により、息子に対してイライラが減った
- 子どもの気持ちを知れて、価値観が広がった
- 自分で固めてきた固定概念から解放され、新しい事を知るきっかけになった
- どんな風にサポートしてあげればいいのか明確になったので、家でのサポートが楽しみになった
- 進学などで今後身近で発達支援の現場を見る可能性のある娘にも、詳しく説明出来るようになった。
実はこの記事は夫を含め、自分の家族に見てもらおうと作りました。
本を1冊渡しても良かったのですが、それでは多分…読まれない笑
それじゃあ私が【知りたかった/得た知識】を簡単にまとめようと書き始めたのが始まりでした。
これをきっかけに詳しく知りたい所は本を読んでもらったり、話すきっかけになるといいなと思います。

絵カードがたくさん載っている本も注文しました!
息子は発達支援が必要と断定された訳ではありませんが、家でできる事があるならば家族で楽しみながらチャレンジして見ようと思います♪
Twitterで友人(オカクミさん:明るくて元気をもらえる文章を書かれる方です!)に教えてもらった電子書籍も、これから読もうと思います!!
最後まで閲覧、ありがとうございました♪
⬇︎電子書籍はコチラ⬇︎
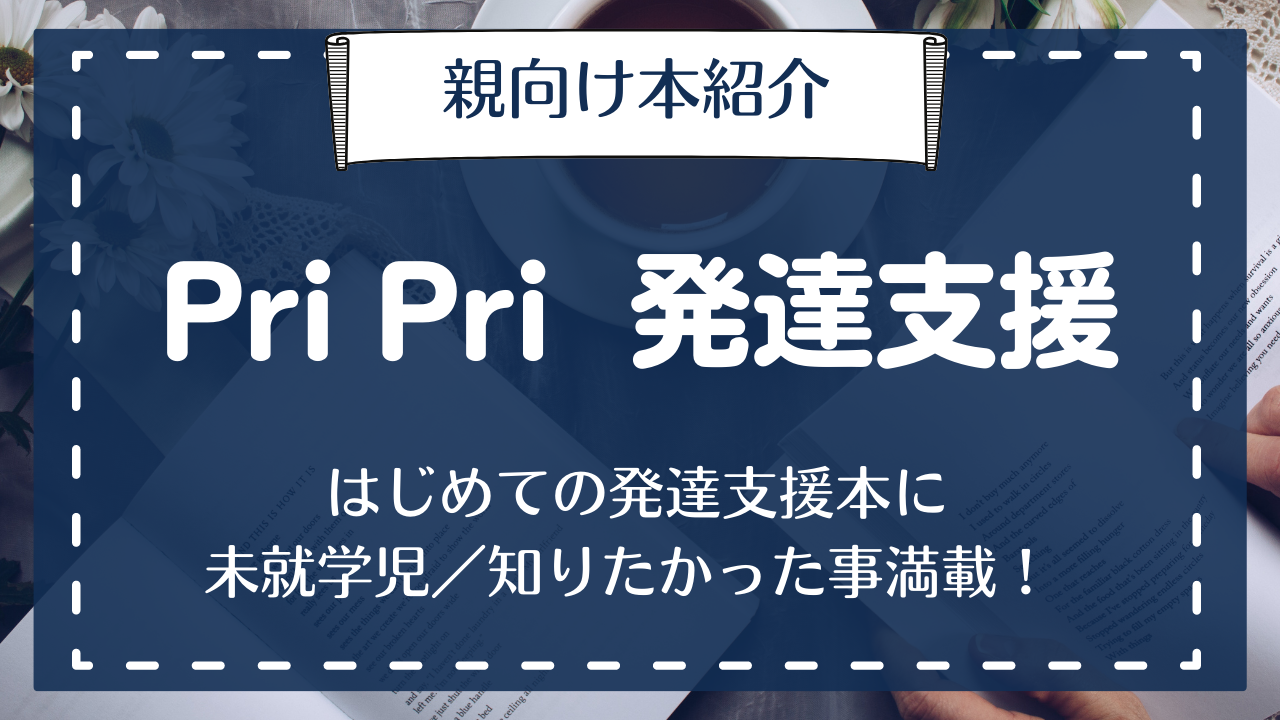

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f831e35.4a50f270.1f831e36.8c500625/?me_id=1213310&item_id=19130036&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7188%2F9784418187188.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント